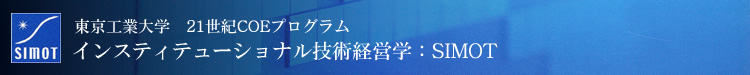 |
|
|
コラム:「記者の眼」
「インスティテューショナル技術経営学」拠点形成活動の状況や成果について、日経BPの記者が拠点メンバーに取材を実施してコラム:「記者の眼」を作成することが決定しました。記事は2ヶ月に1本のペースで作成されます。記事本文をこのページに掲載していきます。 第2回:シンポジウムを通して考えさせられた「実学」としての可能性「具体的な事例をうまく集めることができれば、インスティテューショナル技術経営学がビジネス・パーソンの役に立つ可能性はかなり高そうだ」。 技術経営戦略誌「日経ビズテック」の中国特集の取材で現地のビジネス事情に詳しい「専門家」に会って話を聞いたり、中国華南地域の一大生産拠点である深セン市の日系メーカーの工場を訪問したりする中で、こうした思いを強く抱いた。 中国で感じた存在意義前回のコラムでも書いたように、東京工業大学の21世紀COEプログラム「インスティテューショナル技術経営学」の目的は、国や地域ごとに異なる文化や慣習といった市場の独自性とビジネスの成否との関係を解明することにあると受け止めている。この解釈は、プログラムのリーダーである東工大教授の渡辺千仭(ちひろ)氏ら複数の関係者の説明を総合して得たものだ。 先の特集記事の取材で中国における日本企業の成功と失敗の実例を聞いているうちに、こうした切り口のイノベーション研究が重要であるとの印象が改めて強まったのである。 例えば、典型的な失敗例として挙がったのがビデオデッキのケースである。日本のメーカーは、日本国内で販売している製品をそのまま持ち込んで失敗した。その背景にはビデオデッキの使われ方の違いがあった。 決定的な違いは、中国の人たちは録画予約の機能をほとんど使わないことである。極端にいえば、録画機能そのものを必要としていない。中国のテレビはすべて国営放送で面白い番組がほとんどないからだ。だから予約機能を使ってまで録画しようとは思わない。 ビデオデッキを中国の人たちが使うのは、主にカラオケを楽しむためである。録画予約の機能よりもマイクの接続端子が複数あってエコーの効いた音響性能を備えたビデオデッキの方が売れる。このことに気が付かずに国内の売れ筋商品をそのまま販売したから失敗したわけだ。 在日中国人ジャーナリストの莫邦富(モー・バンフ)氏は次のように喝破する。 「欧米に進出した日系企業は、地元文化に学び、敬意をもって良き企業市民となるべく努力を続けているように見える。しかし、中国ではこうした努力を目にすることは少ない。実態はともかく、あまりに目立たない」。 このような莫氏の指摘の中に、インスティテューショナル技術経営学の大きな存在意義を見いだすことができるはずだ。莫氏の寄稿をはじめとする特集記事「中国リスクの正体」は、3月29日に発売する日経ビズテック第6号に掲載している。 顧客はだれなのか深センから帰国して2日後の2月28日に、同COEプログラム主催の国際シンポジウム「イノベーションとインスティテューションとの共進化ダイナミズムの解明」が始まった。 前回のコラムでシンポジウムの内容に注文を付けたこともあって、開催日の2日間とも東工大構内の会場に通い詰めた。初日は、国際MOT(マネジメント・オブ・テクノロジー)学会の会長を務める米マイアミ大学教授のタレク・クハリル氏をはじめ、日米欧中印の各国の研究者による英語の講演が続く。 いささか気になったのは、プログラムのリーダーである渡辺氏も英語で講演した点だ。同時通訳のサービスが付いているとはいえ、「顧客」である聴衆の大半は日本人。しかも、大多数は学者ではなく企業で働くビジネス・パーソンだったと聞く。 彼らの目に、英語で講演する日本人学者の姿はどう映っただろうか。自分たちに向けられたメッセージではない、さらに言えば、自分たちとは遠い世界での話だと受け止められたとしたら、実にもったいないことである。 このCOEプログラムは、5年かけてインスティテューショナル技術経営学の研究拠点を築くことを目標の一つに掲げている。技術経営、あるいはMOTの研究拠点の形成を目指すのであれば、実例研究などにおいて企業の力を借りることが必要になるだろう。 もし、将来の共同研究の相手となり得るビジネス・パーソンたちから「私たちとは関係のないものだ」と思われたら、共同研究など全くおぼつかない。ささいなことかもしれないが、こうした小さなところから、大きな問題の一端がうかがわれるような気がしないでもない。 企業人の危機意識の共有を初日の会場で、取材でお世話になった人の姿を見つけた。経営コンサルタント会社の出身で現在は都内の大学のビジネススクール教授として活躍している。彼にシンポジウムの感想を聞いたところ、次のような答えが返ってきた。「基調講演だから仕方がないのかもしれないが、すぐにビジネスに役立つ内容ではなさそうだ」。 これでビジネス・パーソンたちの満足が得られるのであろうか。シンポジウムが進むにつれて頭をもたげてきたこんな不安が多少なりとも解消されたのは、2日目の最後に行われたパネル・ディスカッションを聴いたときだ。 特任教授としてこの4月からインスティテューショナル技術経営学の研究と博士課程の学生の指導に携わる6人の企業人が登壇し、自らの実務を通して感じている技術経営をめぐる問題についてそれぞれ紹介した。 例えば、東芝セミコンダクタ提携・戦略担当部長の安田洋史氏は、韓国や台湾などのメーカーの台頭によって激化する国際競争において日本メーカーが競争力を維持していくには、経営資源をうまく生かす総合的な戦略が必要であると主張した。 マイクロソフト業務執行役員ビジネスソリューション本部長の保々雅世氏は、IT(情報技術)の活用に立ち遅れた日本企業でITの活用を最大化するためには、ITそのものの知識よりも技術の動向を踏まえて広く企業全体におけるITの最適化やビジネスモデルの構築を行える人材が必要だと語った。 企業などで競争の厳しさを肌身で知っている特任教授の方々の危機感に基づく問題意識を広く共有することができれば、インスティテューショナル技術経営学は、ビジネス・パーソンの実務に役立つという意味での「実学」に十分になり得るだろう。そう思い返しながら帰路に着いた。 (中野目 純一=日経ビズテック記者) © 2005 Tokyo Institute of Technology, All Rights Reserved.
|