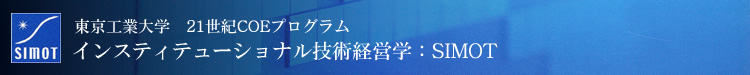 |
|
|
コラム:「記者の眼」
「インスティテューショナル技術経営学」拠点形成活動の状況や成果について、日経BPの記者が拠点メンバーに取材を実施してコラム:「記者の眼」を作成することが決定しました。記事は2ヶ月に1本のペースで作成されます。記事本文をこのページに掲載していきます。 第4回:キルヒャー特任教授との対話で改めて考えた新市場創造の道
前回の本コラムでは、この21世紀COEプログラム 鮫島氏をインタビューの最初の相手に選んだのは、2月に開かれたインスティテューショナル技術経営学の国際シンポジウムにおける同氏の講演が面白かったからだ。そこでインタビューの次の相手としても、同様にシンポジウムでの講演の内容が興味深かった特任教授のローランド・キルヒャー氏を選んだ。同氏は独シーメンスの日本支社で技術推進室室長を務めている。 シーメンスは、世界190カ国に拠点を持ち、43万人の従業員を擁する欧州最大の総合電機メーカーである。その事業領域は情報通信、発電設備、医療機器、交通システム、工場の自動化など幅広い。キルヒャー氏が率いる日本支社の技術推進室は、ドイツ本社の技術本部の窓口として日本企業との橋渡しをするだけでなく、日本の企業や研究機関との共同研究開発プロジェクトの推進役も果たしている。 市場調査では新市場を創れないキルヒャー氏はシンポジウムで企業の研究開発の変化をテーマに講演した。記者とのインタビューにおいても、市場の要求や顧客のニーズを重視して研究開発を行う傾向が強まり、それに応じて中央研究所から事業部門への研究開発機能の移転が進むなど、研究開発組織のあり方が段階的に変わってきていると指摘した。 特に現在は、グローバル化の進展に伴って、市場となる国ごとに研究所を設置し、市場のニーズに応じた製品を素早く開発しようとする企業の動きが広がっているという。この点は、国や地域ごとに異なる文化や慣習といった市場の独自性とイノベーションの成否の関係を解明するという、インスティテューショナル技術経営学の目的と相通じる。 ここまで話をうかがったところで、一つの疑問が再び頭をもたげてきた。このインタビューの前から、ずっと頭を離れなかった問いである。 話は、「イノベーションのジレンマ」の著者として有名な米ハーバード・ビジネススクール教授のクレイトン・クリステンセン氏にインタビューしたときにさかのぼる。業績不振が長引くソニーの再生策について見解をうかがうのが目的だった。 同スクールの研究室で会ったクリステンセン氏はソニーの不振の遠因を、1982年を境に「破壊的技術(Disruptive Technology)」を生み出せなくなったことに求めた。 破壊的技術とは、それまで存在しなかった新市場を創造し既存の企業を破滅に追い込むシンプルで低コストの技術を指す。ソニーが世に送り出した破壊的技術の代表例は、携帯型音楽プレーヤーの市場を創造した「ウォークマン」だ。この画期的な製品は、ステレオ・システムのメーカーを窮地に陥れた。 クリステンセン氏によれば、ソニーは82年まで12の破壊的技術を生み出したが、それ以降は破壊的技術を世に送り出していない。ノート型パソコンの「VAIO」やゲーム機の「プレイステーション」といったヒット商品にしても、既存の市場の製品を改良したものにすぎず、新しい市場を創造してはいない。 破壊的技術を生み出せなくなった原因として、クリステンセン氏は82年以降にソニーがマーケティングに力を入れるようになったことを挙げる。そして、その背景には創業者の盛田昭夫氏が経営の最前線から身を引いたことがあるとみる。盛田氏とその側近は市場調査をしないことを信条としていた。存在しない市場を創り出そうとするときに市場を調査しても無駄であると考えていたからだ。 何を造るべきか迷うメーカーこうした鋭い分析を披露したクリステンセン氏が、ソニーについてどのような再生策を示したのか。それは日経ビズテック第7号の特集記事をご覧いただくとして、同氏のインタビューを終えた後にずっと気にかかっていたのは、いかにして新しい製品やサービスを生み出し、それまでにない市場を創り出すかということである。 これは日本のメーカーの技術者たちにも共通した悩みのようだ。長年NECの研究開発部門のトップを務めてきた半導体先端テクノロジーズ代表取締役社長の渡辺久恒氏はこう言う。「競争力を高めることが企業の至上命題で、そのバロメーターがシェアである。ではシェアを上げるにはどうしたらいいのか。多くのメーカーが悩んでいるのがその問題だ。要は、技術力や研究開発力の以前に、何を作ったらいいのか分からないのだ」。 クリステンセン氏によれば、盛田氏たちは世界中を飛び回り、人々の行動を観察しながら彼らの潜在的な欲求を探り出し、その実現に自社の技術がどう役立つかを考えたという。何となく分かるような気もするが、もう一つ腑に落ちない。 そこでキルヒャー氏にシーメンスでは同様の問題にどのように対処しているかを聞こうと思い立ち、「既存の市場や顧客を重視しすぎると、クリステンセン氏の提唱する破壊的技術に直面する可能性があるのではないか」と水を向けた。 「シナリオ」は突破口になり得るかするとキルヒャー氏は次のように答えた。「その通り。そこでわが社では『シナリオ・プランニング』という手法を応用して、遠い先の未来に実現しそうな社会の姿を描いた未来図を作成することで、誤った技術を開発したり、破壊的技術を無視したりする危険を防ごうとしている」。 同氏によれば、個人のニーズの変化や社会の発展状況、法律や規制といった政治的要因、経済成長や資源の状況などの経済的要因、環境の変化など様々なファクターを考慮して、「未来の展望(Pictures of the Future)」と呼ぶ未来図を作成する。そして未来図の実現に必要な技術や製品、事業を導き出し、その開発に取り組んでいるという。 「我々は未来図の作成を通して未来を予測しようとはしているのではなく、未来図で描いた未来を形成することを目指している」(キルヒャー氏)。 未来を予測するのではなく、自ら創り出す──。こう書くと、いかにも大それたことのように聞こえるが、案外そうでもないのかもしれない。例えば、今や生活必需品になった携帯電話機も、一昔前は夢の道具であった。「肯定的な意味で夢を見る」(キルヒャー氏)ことが、新市場創造の突破口になるのかもしれない。 もっとも、技術者の夢は必ずしも企業に利益をもたらすわけではない。失敗例は数多いのだ。例えば、米モトローラのイリジウム計画。66個の低地球軌道衛星を使って、地球上のあらゆる場所で携帯電話を使えるようにする計画だった。 イリジウム計画をめぐるモトローラの失敗を研究した米ダートマス大学教授のシドニー・フィンケルシュタイン氏は記者にこう語った。 「一連の大きな障害を無視したことが原因だ。例えば1990年代半ばに地上通信による携帯電話サービスが広く普及し、衛星を使ったサービスが意味をなさなくなった。それにもかかわらず、モトローラの子会社であるイリジウム社は何十億米ドルもの資金を使って衛星を打ち上げた」。 一つの夢はしばしば、ほかの夢が実現することで色あせてしまうということなのだろう。夢を見るのも簡単ではない。 (中野目 純一=日経ビズテック記者) © 2005 Tokyo Institute of Technology, All Rights Reserved.
|